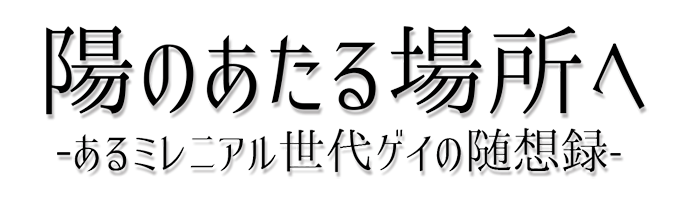皆さま、新年あけましておめでとうございます。いろいろな出来事があった2016年も終わり、いよいよスタートした2017年。皆さまにとって良き一年になるよう、心よりお祈りしております。
さて、いつもは東京で働くゲイのひとりとして、身近な出来事を取り上げて書いている筆者ですが、今回は少し目線を変えて、2017年の世界の動きとLGBTの今後について考えてみたいと思います。
2016年は欧米社会の分岐点となる年だった
2016年は世界、特に欧米社会においては、歴史に残る分岐点の年となったのではないでしょうか。中でも筆者は2つの出来事がとても印象に残っています。
その1つが、6月に行われたイギリスの欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票で、離脱派が勝利したことです。この国民投票においては、当時のキャメロン首相や野党第一党である労働党のコービン党首も揃って残留を主張し、ロンドンに支社を置くグローバル企業等も残留派の運動に多額の資金援助をしていたことなどから、残留派の優勢が伝えられていました。
しかし、実際には離脱派が勝利を納め、イギリスは欧州連合と離脱の手続きに入ることとなりました。
離脱派の主な主張は、表向きは「私たちは欧州連合に決定権を譲渡し過ぎた。国としての主権を回復させる」というものでしたが、実際には「もうこれ以上、移民や難民を受け入れたくない」というイギリス国民の本音が反映された投票結果であったという見方が妥当とされています。
中東でのイスラム国の侵攻による情勢の不安定化や内戦の激化の影響もあり、近年シリアやイラク、北アフリカなどから欧州連合加盟国への難民受け入れ問題が深刻化しています。
イギリスは、その高い水準の社会保障や福祉制度から、難民にとって大変人気のある国と言われています。難民の多くは地中海を渡りイタリアやギリシアに流れ着くわけですが、一度欧州連合加盟国内で難民として受け入れられれば、欧州連合加盟国内は自由に往来することができるようになり、人気のあるイギリスを目指す難民も少なくなかったというわけです。
難民を受け入れた場合、その衣食住の費用負担は税金から賄われます。また難民たちは当然、新天地で仕事を探すわけですから、本来そこで働いていたイギリス人と雇用を奪い合うこととなります。
その上、難民たちは非常に低い賃金水準でもかまわず働くため、皮肉にもそれが全労働者の賃金水準を押し下げているという指摘もなされています。
イギリス人にとっては、自分たちの税金が本来使われるべき公共サービスなどには使われず、雇用を奪われ、賃金水準も押し下げられているということになり、日に日に移民・難民政策に不満を抱くようになっていました。
しかし、欧州連合には加盟国は難民受け入れを拒否できないという法律があります。これにより、イギリスは決して財政基盤が盤石とは言えない国であるにも関わらず、難民を受け入れ続けるしかなく、国民の不満は臨界点にまで達してしまい、今回の離脱派の勝利という結果を生んだのだと思われます。
20世紀後半から21世紀初頭の世界の大きな潮流は「グローバリゼーション」でした。簡単に言えば、ヒト、モノ、カネが国境を超えて自由に往来できることこそが経済の活性化につながり、多くの富と幸福をもたらすという理論に基づいた思想で、日本を含めた先進国の多くはこのグローバリゼーションを支持しました。
特に欧州連合はこのグローバリゼーションの最先端を行く組織であり、イギリスはその中でも中核を成す国のひとつだったわけで、このイギリスが「グローバリゼーション」を否定し、その対極をなす思想である「自国第一主義」つまり「ナショナリズム」に大きく舵を切ったとも取れるわけで、筆者もこのニュースには大変驚きました。
その5ヶ月後、アメリカでも同じことが…
「移民が職を奪っている」「自分たちの大切な税金が彼らに使われている」「働く人の賃金を彼らが押し下げている」等…これらの主張には聞き覚えがあるかもしれません。
この主張は11月に行われたアメリカ大統領選挙で勝利を納めたドナルド・トランプ次期大統領の主張とそのまま重なります。
彼は移民に対する厳しい態度を取るとともに、対抗馬のヒラリー・クリントン氏が、経済のグローバル化をリードして推し進めてきたウォール街の証券会社等から多額の献金をもらっていることを度々批判しました。
選挙活動中に何度も彼が叫んだ「America first」は、読んで字のごとく「自国第一主義」と言う意味であり、グローバル化が進みすぎた今、移民や様々なマイノリティが、多数派のアメリカ国民の平穏な暮らしを脅かしているという主張を繰り返しました。
その主張は、アメリカ国民がなんとなく思っていてもあまり口に出せなかった移民への不満や、マイノリティへの配慮などに疲れてしまっていた心理にうまく入り込み、支持を広げて行き、果てには彼を大統領の座へと導きました。
つまり、これまで様々なバックグラウンドを持った移民を受け入れ、彼らの働く意欲や野心をそのまま国家の原動力に変換させることで国を成長させてきたアメリカ合衆国という国が、イギリスに続いて「グローバリゼーション」から「ナショナリズム」に大きく舵を切ったというわけです。
つまり2016年という年は、20世紀後半から続いてきた「グローバリゼーション」を中心となって推し進めて来た2つの大国が相次いでその潮流から離脱した年として、歴史上重要な分岐点であったと記録されることになると思います。
2017年も続くと予測される「ナショナリズム化」の潮流
そして2017年も、世界のこの大きな流れは続くものと予測されています。4月~5月にかけて、フランス大統領選が予定されています。
フランスと言えば、現職のオランド大統領が就任早々に同性婚を合法化するなどして、一時期脚光を浴びました。しかしここ最近では、移民による深刻なテロが多発しており、フランスに関するニュースは物騒なものが増えてきています。
その上、前大統領であるサルコジ氏も、現職のオランド大統領も、揃って雇用政策に失敗しており、共和党と社会党という既存の二大政党制に対する大きな失望感が国民の間には漂っていると聞きます。
そこに浮上したのが、国民戦線という極右政党です。彼らはまず、高止まりした失業率は、大量の移民を受け入れたことによるものだと主張しています。また、頻発するテロ事件とも絡め、フランス国民を脅かせる要因はすべて国外からもたらされたものであり、つまり、グローバリゼーションが進みすぎたことによって起きたものであると主張し、EUからの離脱や移民排斥などの公約を掲げています。
国民戦線自体は古くからある政党でしたが、長年少数政党として強い発言力は持たない組織でした。しかし、近年この政党は党勢を拡大し、ついには同党党首のルペン氏が次期大統領選の有力候補として名前が上がるほどの情勢になっています。
例えルペン氏が大統領に選ばれなかったとしても、一定の支持を集めている以上次期大統領はある程度は国民戦線の掲げている、ナショナリズム色の強い政策決定をしていく必要に迫られるかもしれません。
理想主義、性善説に立ちすぎたドイツの移民政策
そして、2017年の9月にはドイツの連邦議会選挙が予定されています。長年、堅実な政権運営と安定した経済情勢によって「ヨーロッパの優等生」「欧州連合の盟主」と呼ばれてきたドイツですが、2017年はドイツにとっても大きな転換期となるでしょう。
ドイツのメルケル首相は、東欧方面から難民や移民を大量に乗せた列車がドイツに到達し続ける現状を目の前にしても、人道的視点から難民を受け入れ続けました。
結果、ドイツには難民・移民が100万人以上も流入することとなり、受け入れ体制がパンク寸前になっていたのは、ニュースでも度々報道されていました。
つまり、ドイツも前述したイギリスやアメリカ、フランスと同じ状況に陥っており、国民の間でも難民や移民に対する反感が広まっています。(しかも、2016年暮れのクリスマスマーケットでもテロ事件が起きてしまいました)
こうした国民感情を反映してか、2016年にあった地方選挙では、メルケル首相率いるキリスト教民主同盟は次々と惨敗。メルケル首相自身も、敗北の原因は移民政策にあったことを素直に認めています。
その代わりに躍進を遂げたのが、新興極右政党の「ドイツのための選択肢」です。この政党も、例によって移民排斥、欧州連合離脱を主張するナショナリズム色の強い政党です。連邦議会選挙を前に、この極右政党は支持率を伸ばし続け、2016年秋の世論調査では2大政党に次ぐ支持率を獲得するまでの勢いを見せています。
こうした現状を受けてか、メルケル首相は2016年12月に難民・移民の受け入れの厳格化と、ドイツ国内でのブルカ、ニカブ(イスラム教徒の女性が身につける黒いベール)の着用禁止を支持する声明を発表しました。
これは「ドイツのための選択肢」の躍進を受けた方針転換であることは明らかで、今後ドイツもナショナリズム的政策に転換して行くものと思われます。
欧米のナショナリズムとLGBT政策
ここまで、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツについて解説してきましたが、こうした欧米の主要国が次々とナショナリズムに政策転換をしていくと、各国のLGBTにとってどんな影響があるでしょうか。
率直に言って、LGBT政策に関してはあまり良い方向に進むことは期待できないでしょう。
あまり難民の受け入れ経験がなく、周辺を海に囲まれた島国であるため近隣国からの移民も多いわけではない日本では、「社会的マイノリティ」は庇護を受ける存在ではあっても、それがそのまま平和や安全を脅かす存在という認識は薄いかもしれません。
しかし、移民国家であるアメリカや、政治的・経済的情勢の不安定さを抱える国々と陸続きの欧州主要国では、社会的マイノリティが国民の平和や安全を脅かす存在であるという認識を持つ層の人々も少なくありません。
加えて、これらのキリスト教徒の国々においては、その社会的マイノリティの中にキリスト教以外の宗教を信じる人々や、元々キリスト教では存在を認められていなかった同性愛者等の性的少数者もその「脅威」に含んだ上で、ナショナリズムを掲げる極右政党から攻撃対象とされる傾向があります。
今回、例に挙げたイギリス、アメリカ、フランス、ドイツは、どこも近年LGBTに対して寛容な態度を示して来た国々です。アメリカも、連邦最高裁判所が同性婚の禁止は違憲という判決を下し、オバマ大統領がこの判決を支持したばかりです。
当初トランプ次期大統領は実はLGBTフレンドリーなのではないかという憶測も飛び交いましたが、側近の人事が固まっていくにつれ、LGBTに対しても強硬な姿勢を取る人選が目立って来ています。
しかし、日本やアジアは暗い話ばかりではない
翻って、我が国はどうでしょうか。
LGBTビジネスや自治体のパートナーシップ制度は不発の感が否めないですが、それは裏を返せばもともとLGBTであることで身の危険を感じたり、生活に決定的な不便さを感じたりするような激しい差別が、欧米よりも少なかったという解釈をする向きも少なくありません。
同時に、これまでの日本のLGBTアクティビズムは、やや欧米信仰が強すぎたのではないかという印象を筆者は持っています。
これまで見てきたように、欧米と日本とでは「社会的マイノリティ」という言葉から連想するイメージや社会が示してきた態度もまったく違います。宗教観や社会的背景がまったく違うため、LGBT当事者が感じているニーズも欧米と日本とでは違ったものになるのは必然的なことです。
この差異を無視して、欧米はLGBT施策が進んでいて日本は遅れているからと自国の批判に終始し、「欧米を知っている自分がもっと先進的なLGBT施策を広めなければ」という宣教師的な使命感によって成立する社会運動は、そもそもその欧米がLGBTに不寛容な態度に転換したら論理的後ろ盾を失うため、非常に危うい側面を持っているものでした。
欧米社会が大きくナショナリズムに舵を切った今こそ、日本は日本として、欧米の制度やニーズからは自立した独自のニーズ調査や制度設計に着手して行くフェーズに到達してきているのかもしれません。
また、台湾では2016年暮れから同性婚を可能にするための民法改正案が審議されており、早ければ2017年の春にはアジアで初の同性婚が実現する可能性も現実味を帯びてきました。
これには、2016年に台湾が国民党から民進党に政権交代を果たしたことも大きく関係しています。
現在、台湾総統を勤める民進党の蔡英文氏は、野党時代からLGBTの政策には熱心に取り組んでおり、それを引き合いに出して敵対勢力からレズビアン疑惑をかけられたことがありました。
最後に、これを追求された時の蔡英文氏の反論を紹介しておきたいと思います。
「(自身のセクシュアリティに関して)私にそれを答える義務はない。それどころか、そういった質問が誰かを圧迫する手段に使われてはならない」
なんとも心強い言葉です。
この、欧米主要国の転換期をうまくチャンスに変えて行けるかどうか、日本やアジアのLGBTにとって2017年は正念場の年となるかもしれません。